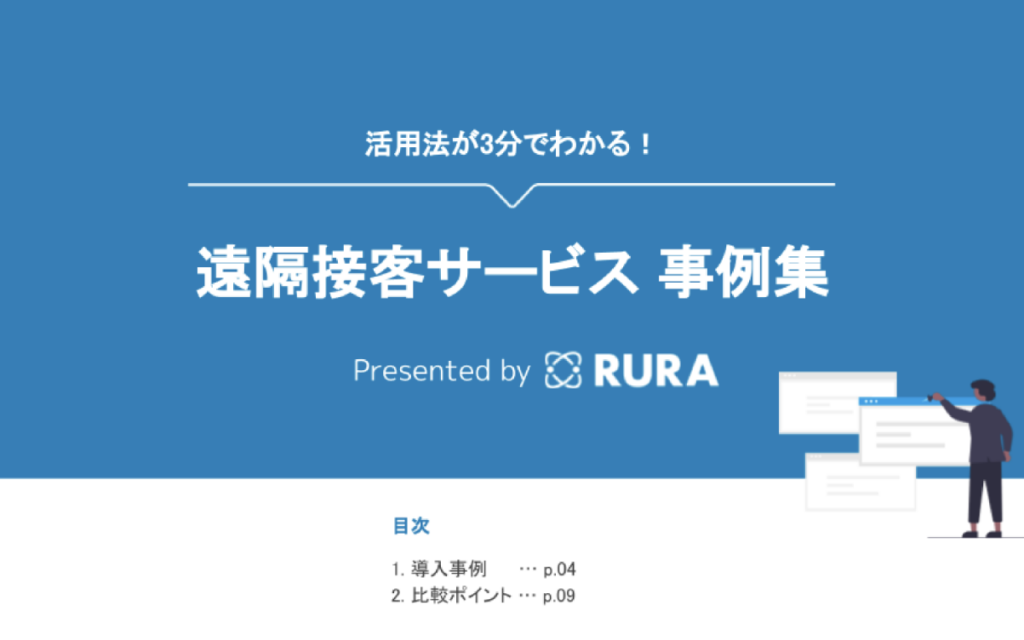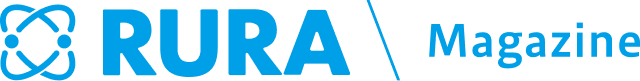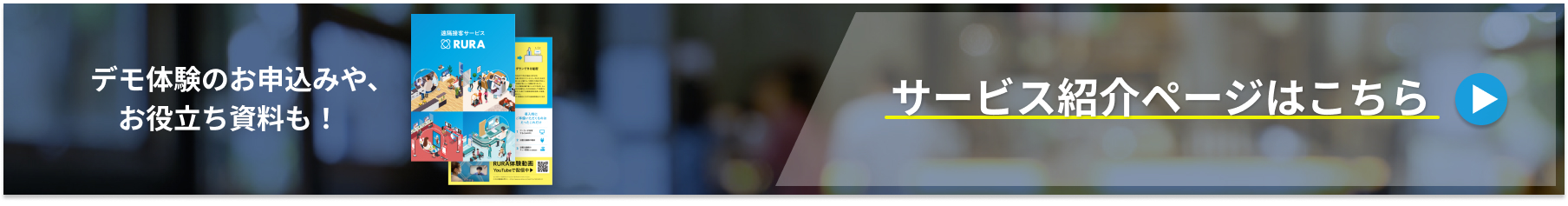「インバウンド対応って、何から始めればいいのか分からない」「外国人観光客を受け入れる準備って、そんなに必要?」そう思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、そうした「今やっておくべきこと」を具体的に解説しながら、実際に成果を上げている取り組みや事例も交えてご紹介します。これからインバウンド対応に取り組む方、見直しを検討している方はぜひご一読ください。
インバウンド対応が求められる背景とは?
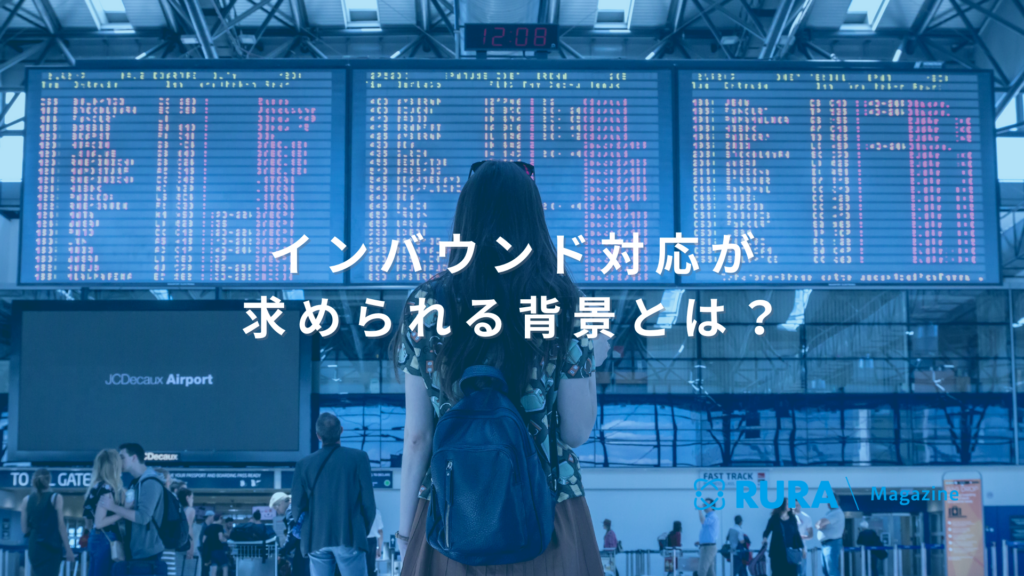
訪日外国人観光客の増加とその影響
日本を訪れる外国人観光客は、近年再び急増しています。特にアジア圏からの観光客は、円安の影響もあり「今こそ日本へ行きたい」というモチベーションが高く、観光地・商業施設にとっては大きなビジネスチャンスです。
2024年の訪日外客数は年間3,687万9,400人に達し、過去最高だった2019年(3,188万人)を上回る水準となりました(出典:日本政府観光局〈JNTO〉「訪日外客数(2024年12月推計値)」)。
SNSやレビューサイトを通じてその価値が拡散される今、地域の魅力や接客体験が可視化され、観光そのものが“共有される体験”として進化しています。インバウンド対応の質がそのままブランド評価に直結する時代が到来しています。
ポストコロナで変わった観光業の課題
新型コロナを経て、観光業には“安全性”や“効率性”が重視されるようになりました。単なる言語対応では不十分で、非対面や非接触といった配慮が求められます。また、慢性的な人手不足という構造課題も重なり、現場ではよりスマートで持続可能なオペレーションが必要とされています。
地方都市や中小事業者にもチャンスが広がる理由
「体験型観光」「地域の暮らしを感じたい」といった需要の高まりは、地方の小規模施設にも十分な可能性をもたらします。魅力的な観光資源があるにもかかわらず、“対応の未整備”がネックとなっている地域は少なくありません。今こそ、小さく始めて大きな効果を生むインバウンド対応が求められています。
インバウンド対応でやっておくべきこと5選
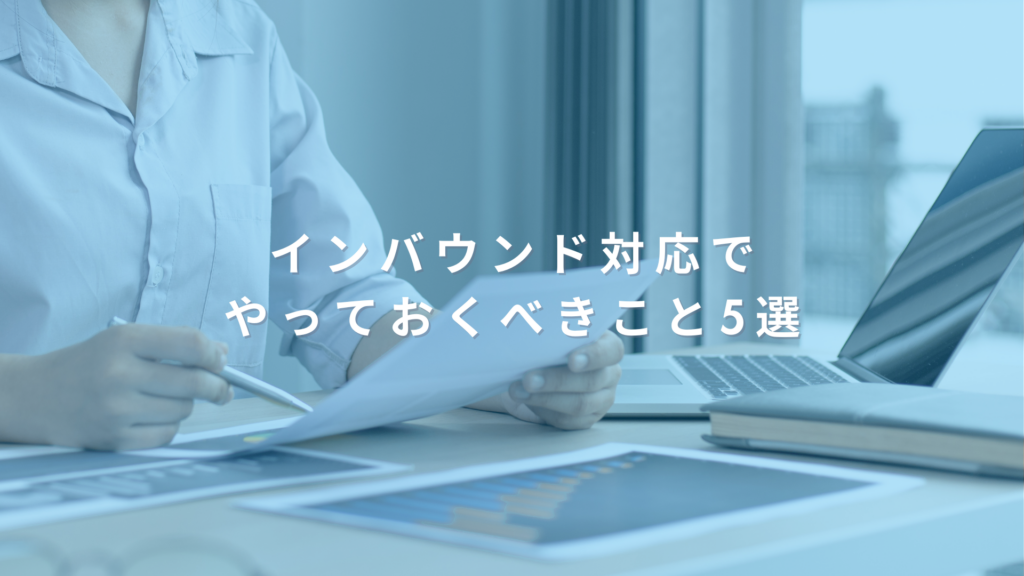
多言語での案内表示や接客体制の構築
最も基本的かつ重要なのが、言語の壁を乗り越えることです。施設内の案内表示を多言語化し、最低限のコミュニケーションが可能な体制を整えるだけで、訪問者の満足度は大きく変わります。翻訳アプリや定型文の提示など、予算をかけずに始められる手段も多くあります。
非対面・非接触での接客導入
限られた人手で対応するには、非対面型の接客システムが非常に有効です。離れた場所からリアルタイムで接客ができる遠隔対応の仕組みは、業務効率化とサービス品質の両立に役立ちます。こうしたツールは、後述する「RURA」のような遠隔接客サービスを活用することで実現可能です。
SNSを活用した情報発信の強化
現代の旅行者は、旅先の情報をSNSから得ています。施設の魅力を写真や動画で発信することは、集客につながるだけでなく、“訪れたくなる理由”の創出にもなります。外国語での投稿や、ユーザーによるレビュー共有の導線づくりも重要です。
スタッフ教育とおもてなしの意識改革
文化や価値観の違いに配慮することは、真のおもてなしにつながります。礼儀作法、宗教的背景、食事制限への理解など、外国人への対応力を高める教育が欠かせません。マニュアル化と同時に、現場での応用力を養うことが求められます。
国や自治体の支援制度の活用
多言語対応や非対面接客の導入には、補助金・助成金の活用も視野に入れるべきです。観光庁や自治体による支援制度は年々拡充されており、うまく利用すれば予算を抑えて効率的に整備を進められます。
多言語対応のコツとおすすめツール

多言語対応で押さえるべき3つの領域
表記・サイン類
施設の中で最も目に触れるのが案内表示です。誰にでも伝わるピクトグラムと簡潔な多言語表記を組み合わせることで、安心感と分かりやすさを提供できます。
接客・会話対応
スタッフの語学力に依存せず、翻訳アプリやフレーズカードなどのサポートを導入することで、現場の負担を軽減しながらスムーズな接客が可能になります。
デジタルコンテンツ
Webサイトやパンフレットを英語・中国語・韓国語に対応させることも基本的な取り組みです。特にスマートフォンからの閲覧に最適化された構成が求められます。
無料・有料のおすすめ翻訳ツール紹介
Google翻訳など、無料でも高品質なツールが揃っています。対面での会話に便利なポケトークなども含め、現場のニーズに合った選定が鍵を握ります。
多言語対応の成功事例に学ぶ実践のヒント
とある観光地では、地域一帯で案内板を統一・多言語化し、口コミでの評価が飛躍的に向上しました。統一感と丁寧さが訪問者の印象を大きく左右する好例です。
非対面接客の重要性と導入事例
なぜ今、非対面接客が注目されているのか?
人手不足が深刻化する一方で、利用者側の利便性やスムーズな体験への期待は年々高まっています。そうした中、効率的かつ柔軟に運営できる“遠隔接客”という選択肢に注目が集まっています。 特に一人のスタッフで複数拠点を同時にカバーできる仕組みは、「省人化」と「サービス品質の両立」が可能になる仕組みとして導入が進んでいます。
非対面でも「おもてなし」は実現できる
遠隔接客では、単なる省人化ではなく、接客品質そのものを均一に高めるという視点が重要です。特に、経験豊富で対応力のあるスタッフが複数拠点を遠隔でカバーできる仕組みは、大きな強みとなります。現地の人員に依存することなく、どの店舗でも“同じレベルのおもてなし”を提供できることで、サービスのばらつきが減り、ブランド価値や顧客満足度の向上につながります。
遠隔接客サービスの活用シーン
小売・観光施設
ホテル・宿泊施設
総合案内所・インフォメーション
それぞれの業種で、遠隔接客は柔軟な活用が可能です。現地のスタッフを減らしながらも、対応品質は落とさずに済む運用が求められています。
遠隔接客サービスRURAを活用した実際の導入事例紹介

遠隔接客サービス「RURA」は、商業施設や空港をはじめ様々な施設に導入が進んでおります。
実際に遠隔接客を本格導入し、成果を挙げている施設の一つが「JR東日本ホテルメッツ」です。「飾らない上質」をテーマに掲げる同ホテルでは、RURAを活用することで接客品質を保ちながら、人員配置の最適化と業務効率化を両立しています。
フロントに設置されたRURAを通じて、別拠点にいるスタッフがリアルタイムでお客様の応対を行い、チェックインや案内対応をスムーズに進めています。多言語対応にも対応しており、訪日外国人からも「リアルタイムなの?」「どこで対応してるの?」と好意的な反応が寄せられているそうです。
また、操作性の高さから新人スタッフでも早期に接客業務に入ることが可能で、教育や研修面でもメリットを感じられているとのことです。「効率化しながらも、これまでのおもてなしの質を守りたい」というニーズに応える仕組みとして評価されており、RURAの導入はホテル全体の運営力向上にも寄与しています。
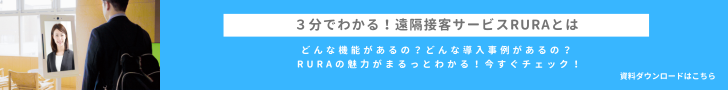
SNS・口コミを活かした情報発信戦略
訪日客が使うプラットフォームとは?
InstagramやYouTubeなど、視覚重視のSNSが主戦場となっています。写真や動画の訴求力はテキスト以上に高く、直感的な魅力が伝わることが重要です。
SNSと連携したプロモーション事例
インフルエンサーとのタイアップや、投稿キャンペーンなどが有効な手段となります。投稿を通じて拡散された情報は、信頼性と親近感を伴って広がります。
外国人ユーザーの声を集める方法と活用法
レビュー収集やアンケートで得たリアルな声は、改善だけでなく、次の顧客への信頼材料にもなります。「生の声」を資産化することが、次の来訪を生み出すきっかけになります。
インバウンド施策に活用できる支援制度
国・自治体の補助金や助成金の概要
観光庁や自治体では、インバウンド対応に関するさまざまな補助制度が用意されています。対象は幅広く、設備投資やソフト整備など多岐にわたります。
どんな施策に使えるのか?具体例紹介
多言語表示の設置、Webサイトの多言語化、遠隔接客端末の導入など、実務レベルで活用できる支出項目が多く含まれています。
応募の流れと注意点
申請には計画書や見積もりが求められます。スケジュール管理や行政との連携も重要になるため、事前の情報収集と準備が成功の鍵となります。
今から始めるインバウンド対応の第一歩とは
小さく始めて大きく育てる考え方
一度にすべてを整えるのではなく、まずはできるところから手を付けることが大切です。案内表示の多言語化や、簡易翻訳ツールの導入からでも充分に始められます。
まず取り組むべき優先度の高い項目
まず整えるべきは、来訪者の不安を取り除く基本的な導線づくりです。言語・接客・情報発信の3つの視点で、自施設を一度見直すことが重要です。
社内や地域での共有・巻き込みの工夫
インバウンド対応は担当者ひとりの力で成し遂げるものではありません。社内や地域全体での意識共有と、実行のための小さな成功体験の積み重ねが長期的な成果につながります。